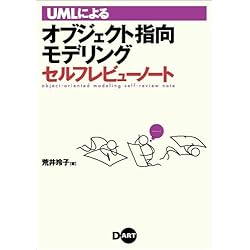- blogs:
- cles::blog

オブジェクト指向モデリングセルフレビューノート

 objectoriented
objectoriented
本屋でボーっと眺めていたら帯の「UMLで書いてみたんですけどあってますか???」という刺激的なフレーズに惹かれて買ってしまいました。というのも、最近後輩からそういう質問をよく受けているからです。
直感的に同意できる部分が多くて、分類もわかりやすいので、そういう意味で面白く(というかすらすら)読めるのはいいんですが、その根拠はちょっと釈然としないところが多いように思います。なんというかヒューリスティクスの塊のような感じといえばいいんでしょうか。初心者というよりは、初心者を指導する先輩役向けの本なのかなと思います。また、レビューについても載っていますが、レビューについて詳しく知りたい場合は「ピア・レビュー」のほうがオススメです。
モデリングに対する評価クライテリアの項目の分類自体はわりとと好きなんですが、具体的にどうすべきかというところまでは触れられていません。クライテリアの項目を見た時点で自分の書いたモデルに対して具体的に何をしなければならないかがわかるような人はいいのですが、そのような人はこの本のスコープではないはずです。
したがって、それができない初心者にそれをいかに気づかせるかということが、この本の主題となってくると思うのですが・・・そのあたりは全体的に甘いと思います*1。おそらくこの本を読んで初心者がセルフレビューを行うことは難しいんじゃないかと思います。
† なんでこの本に惹かれたか
それは「設計してみたんですけどあっていますか?」と大学でたくさんの人からよく聞かれるからです。ソフトウェアは芸術作品ではないので、自分で作ったものの良し悪しがわからないというのはなんとも切ない話です。
大学のカリキュラムを見渡すと、自分の設計を自分で実装する機会がほとんどないのでそれは無理もないのかもしれません。ソフトウェアを作る作業は設計して、実装するというステップがあります。自分で設計して、その通りに実装してみて、さらに機能拡張を行ったり、仕様変更をしてみれば自分の設計が合っていたかどうかということは比較的すぐ理解できることだと思います。自分のことを振り返れば、設計と実装をを繰り返しながら、触媒としてソフトウェア工学を体系的に学ぶことによって、設計や実装のの本質的なことを少しずつ理解できるようになって、現在に至っているのだと思います。
その触媒のひとつにこの本が教科書のように使えないかという目論見だったワケですがこれはどうやら失敗ですね・・・・
- *1: そのあたりは僕が期待しすぎなだけなのかもしれないですけど
このエントリへのTrackbackにはこのURLが必要です→https://blog.cles.jp/item/940
古いエントリについてはコメント制御しているため、即時に反映されないことがあります。
コメントは承認後の表示となります。
OpenIDでログインすると、即時に公開されます。
OpenID を使ってログインすることができます。
2 . RT810 の DHCP サーバを WPAD に対応させる(728)
3 . アーロンチェアのポスチャーフィットを修理(691)
4 . 福岡銀がデマの投稿者への刑事告訴を検討中(666)
5 . シャープの空気清浄加湿器のキュルキュル音対策は PTFE テープで(586)