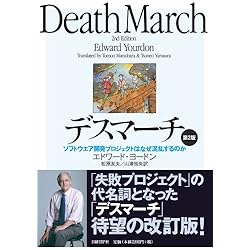- blogs:
- cles::blog

デスマーチ

 softwareengineering
softwareengineering
すっかり世間に浸透したいわゆるデスマの語源になったYourdonの本。出張中にずっと読み直していました。
この本が面白いと思うのは、ソフトウェア設計法の大家であるYourdonが、ともすれば典型的な学者やコンサルにありがちな「このメソッドを使えば、ソフトウェア開発は失敗しない」というような銀の弾丸理論を展開しそうなところを、いい意味で裏切って、プロジェクトの惨状にフォーカスを当てていることに尽きると思います。
確かにソフトウェアプロジェクトは人の問題で頓挫することが多々あり、それを人の問題ということで済ませているのは進歩がないと思っていますので、ソフトウェア開発法である程度技術的にやりきっていない他の人に同じことを言われてもここまで心に響かないというか、リアリティをもって聞くことができないと思います。そのあたりは先日のDeMarcoのピープルウェアについても同じカテゴリの本だと思っています。ということで、この本を読む前にCoad/Yourdon法なんかを勉強しておくと、違った理解があるんじゃないかと。。。。
ちなみに、この本ではデスマーチを下記のように定義しています。
公正かつ客観的にプロジェクトのリスク分析(技術的要因の分析、人員の解析、法的分析、政治的要因の分析も含む)をした場合、失敗する確率が50%を超えるもの。*1
自分自身もデスマなプロジェクトの経験は何度もあって、2004年の4月頃には「プロジェクトの成功は些細なことの積み重ねから」というエントリで自分がどうしてデスマなプロジェクトに入り、どうして乗り切れたのかを書いています。この本の第1章のデスマーチ・プロジェクトに参加する理由の部分を読んでいると、当時の記憶が鮮明に蘇ってきます。
書いてあることはアメリカの文化の話なので、この本で触れられていることを日本のSIerの雇われエンジニアに当てはめるのは難しそうですが、フリーのエンジニアであればそこそこいけるんじゃないかと思います。
- *1: p.4
このエントリへのTrackbackにはこのURLが必要です→https://blog.cles.jp/item/2578
古いエントリについてはコメント制御しているため、即時に反映されないことがあります。
コメントは承認後の表示となります。
OpenIDでログインすると、即時に公開されます。
OpenID を使ってログインすることができます。
2 . RT810 の DHCP サーバを WPAD に対応させる(710)
3 . アーロンチェアのポスチャーフィットを修理(679)
4 . 福岡銀がデマの投稿者への刑事告訴を検討中(654)
5 . シャープの空気清浄加湿器のキュルキュル音対策は PTFE テープで(569)